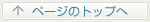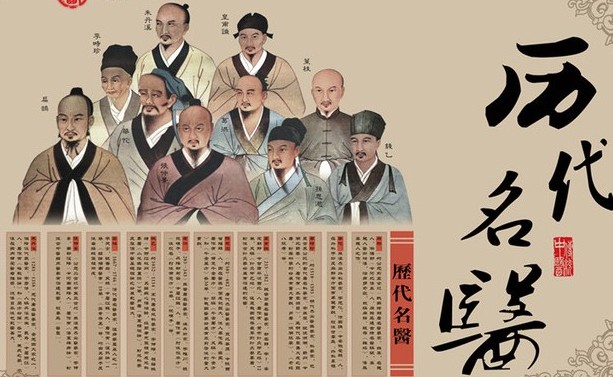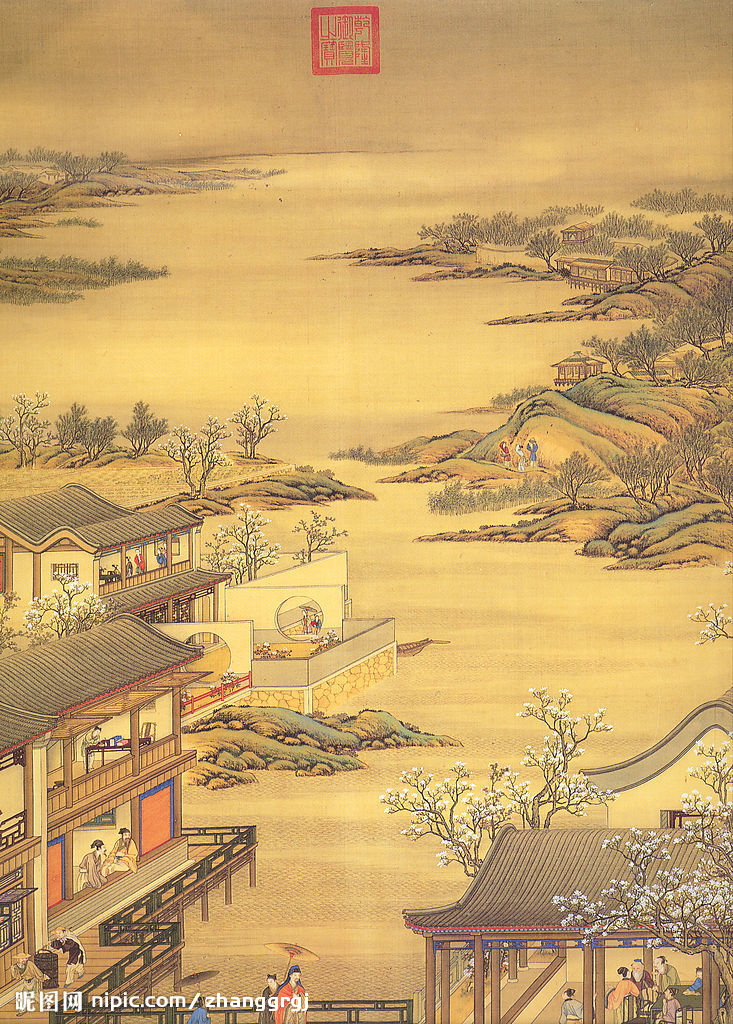〇漢方医学漢方薬の効果と経験症例〇
ベーチェット病は、中医学では「狐惑(こわく)」と呼ばれ、その病因と病態は主に湿熱(しつねつ)や虫蝕(ちゅうしょく)と関連しています。中医学における治療は、中医学の証候論治(しょうごうろんち)の方法を使用し、ベーチェット病患者のさまざまな臨床症状に応じて、内服薬と外用薬を組み合わせて治療することが一般的です。
ベーチェット病は一般的にベーチェット症候群を指し、これは慢性の全身性の炎症性血管疾患であり、遺伝、感染、環境などの要因と関連している可能性があります。患者は口内潰瘍、生殖器潰瘍、眼炎、皮膚損傷などの症状が現れることがあります。ベーチェット症候群は一般的には治癒できませんが、中医学的治療によって症状を軽減することは可能です。
ベーチェット病の患者は、中医学における証候が異なります。一部の患者は主に湿熱が壅盛(おうせい)している可能性があり、他の患者は血瘀(けっよ)の証を合併しているかもしれません。また、肝腎(かんじん)の不足症状を合併している患者もいます。したがって、中医学の治療では、異なる証候に基づいて異なる治療原則と治療計画を立てる必要があります。中医学では、通常、君臣佐使(くんしんさし)と呼ばれる多味薬を組み合わせ、協力して効果を増幅させる役割を果たします。ベーチェット病は西洋医学の風濕免疫疾患に属し、全身の血管炎(けっかんえん)であり、大動脈、中動脈、小動脈、静脈(じょうみゃく)などの血管に影響を及ぼす可能性があります。
日常生活では、口内を清潔に保つように心掛けます。また、十分な睡眠を確保し、夜更かしを避け、適度なジョギングやヨガなどの運動を行うことで免疫力を高めることができます。さらに、漢方専門の先生の指示に従って漢方薬を使用することで、症状を軽減できる場合があります。
中医学ではその病名だけでなく、症状や体格・体質など(「証」といいます)もみて処方を決めます。
「証」に応じた処方を行うことにより、様々な自覚症状も改善が期待されます。
今まで西洋医学また保険診療漢方外来、病院のエキス剤・粉薬・錠剤、他店の煎じ薬などいろいろな方法を試しても満足できなかった方は、東京漢方薬局香港堂の煎じ薬、民間薬をお試し下さい!
【予算費用】煎じ薬:1ヶ月 35,000円(税込)
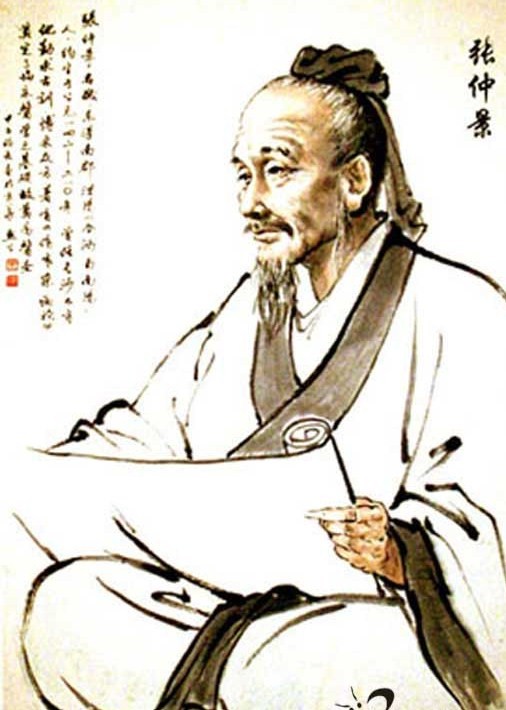
※3か月分以上をまとめて購入する場合は、10%の割引があります。
詳しくはお問合せください。
|完全予約制
●来局での相談は完全予約制となります。予めご予約をお願い致します。
<詳しくは漢方相談料金についてをご覧ください>
- 漢方相談は来店いただくのが一番望ましいですが、ご遠方の方やご都合の悪い場合はメールや電話にてご相談し、漢方を郵送でお届けすることも可能です。
- ※漢方の注文から発送まで数日かかる場合あります。ご不便をおかけしますがご了承頂きますようお願い致します。

●お問い合わせのメールフォームより必要事項をご入力の上、送信してください。
●遠方の方は舌表面の写真1枚が必要です(携帯で写真を撮って下記メールアドレスに送ってください)
メールアドレス:hongkongryuhou@gmail.com
※後ほどこちらから連絡を致しますので、ご自身の電話番号を必ずご記入下さい
電話:0362623935
携帯:09018601469
●安心安全な漢方薬
東京漢方薬局香港堂の漢方はすべて大手漢方生薬メーカーの「ウチダ和漢薬」などから仕入れし「薬局製剤指針」より作られています。安全の確保のためすべての生薬は理化学試験、重金属ヒ素残留農薬管理、微生物など検査済みで高品質なものです。